要約(先に結論)
- 就寝前のスマホやタブレットはメラトニン分泌の抑制と体内時計の遅れを招き、入眠を遅らせる。
- 影響が大きいのは短波長(青~青緑、約460–500nm)×高照度×長時間×就寝直前という条件。
- 実務的には就寝2–3時間前から減光、画面は“最小輝度+暖色”、ベッドに持ち込まないの3原則で十分に効果が出る。
どう眠りを乱す?(仕組みの要点)
- 網膜のメラノプシン含有細胞が短波長の光を強く拾い、**視交叉上核(体内時計)**へ「まだ昼だよ」という合図を送る。
- その結果、夜に高まるはずのメラトニンが抑えられ、**DLMO(メラトニン立ち上がり)**が後ろにずれる。
- スクロールや通知などの認知刺激も覚醒度を上げ、入眠をさらに遅らせる。
今日からできる“3原則+6テク”
3原則
- 時刻:就寝の2–3時間前から画面を減らす(どうしてもの時は“読むだけ”に限定)。
- 光:画面は最小輝度+暖色化、部屋は低照度・暖色に。
- 場所:ベッドに持ち込まない(充電器は寝室外 or ベッドから届かない位置)。
6テク(OS/環境別の実務)
- iPhone/iPad:画面明るさ最小/Night Shift“色温度を最暖に”/True Toneオン/アクセシビリティ→色合いを下げるでさらに暖色化。
- Android:ダークモード/夜間モード(ブルーライト軽減)最大/明るさ自動オフで手動最小。
- PC:Windows「夜間モード」/macOS「Night Shift」+ブラウザのダークテーマ。
- 照明:就寝2–3h前から電球色(~2700K)、スタンドライト中心に。
- 物理対策:紙の本・オフライン読書へ切替え。どうしても端末なら通知OFF+“読書だけ”アプリ。
- 最後の切り札:どうしても仕事がある日は、終了時刻を決めて“シャワー→薄暗い部屋→就床”を固定ルート化。
夜の“最低限ルール”
- ☐ 就寝2–3h前に通知を一括オフ(おやすみモード)
- ☐ 画面は最小輝度+暖色(Night Shift/夜間モード最大)
- ☐ 動画・ゲーム・SNSは就寝1h前まで(残すなら“静的な読書”のみ)
- ☐ 寝室は300lx未満を目安(可能ならそれ以下)
- ☐ ベッドに端末を持ち込まない/充電は寝室外
- ☐ 朝はカーテン全開&屋外光15分で時計を“前に戻す”
よくある悩み → すぐ効くリカバリ
- 「仕事が夜まで延びる」 → 締切前提でOK。終了“1時間前”に通知遮断&暖色化を自動化(ショートカット/規則)。
- 「どうしても動画が見たい」 → 音声だけに切替え(画面OFF再生)。
- 「家族の連絡で通知が必要」 → おやすみモードで特定の相手だけ許可。
- 「早起きがつらい」 → 朝の屋外光(15分〜)を毎日固定、休日の起床は±1時間以内。
受診の目安
- 就寝前の端末制限を2–4週間続けても、入眠困難・中途覚醒が週3回以上かつ日中機能障害がある
- いびき・無呼吸の目撃/強い日中の眠気(睡眠時無呼吸が疑わしい)
- 抑うつ・不安が強く、夜間の使用がやめられない
→ 睡眠医療/メンタルヘルスで評価(CBT-I/併存症の治療を含む)。
医師の監修コメント
臨床では、“ベッドに持ち込まない”だけで入眠が改善する方が少なくありません。完全にゼロにできなくても、**“時刻”と“色温度・輝度”**を管理すると体内時計のずれは小さくできます。朝の屋外光+夜の減光という“時間の両端”を押さえるのが最短ルートです。
参考文献
- Cajochen C. Light, circadian rhythms, and human sleep.
- Chang A-M, et al. Evening use of light-emitting eReaders and sleep.
- Gooley JJ, et al. Spectral sensitivity of human circadian system.
- Wright KP, et al. Circadian misalignment and performance.
- AASM. Recommendations for electronic media use before bedtime.

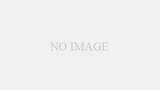
コメント